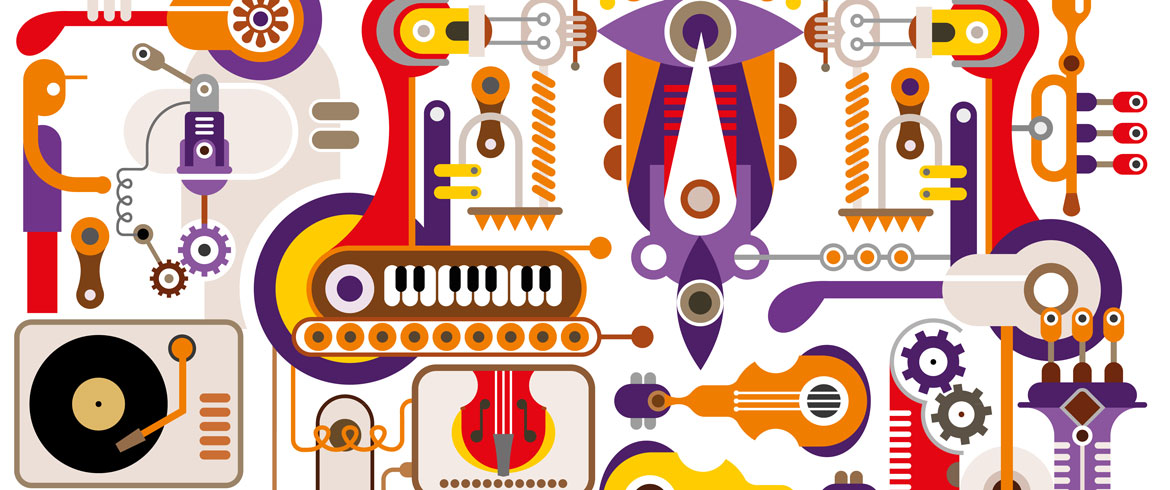目次
除草剤グリホサート、発がん性リスク
2年ほど前になりますが、世界中で使われている除草剤の成分「グリホサート」にさらされると、がんのリスクが41%増大するという研究結果が学術誌に発表されました。
グリホサートはアメリカモンサントの「ラウンドアップ」などの除草剤に使われている化学薬品です。
世界保健機構(WHO)の国際がん研究機関(IARC)は、「人に対して恐らく発がん性がある」グループにグリホサートを分類しました。
一方、アメリカ環境保護庁や欧州食品安全当局は、グリホサートの発がん性に否定的な見解をまとめ、モンサント(かつてベトナム戦争で枯葉剤の製造に関わった)を2018年に買収したバイエル(ドイツ)も、グリホサートの安全性と除草効果を強調していました。
欧州では全面禁止の動き
環境問題や食の安全に関心の高い欧州では、グリホサートを禁止する動きが相次いでいます。
オーストリアでは、国民議会(下院)が、グリホサートの使用を全面禁止にする法案が可決されました。
フランスでは、2017年リヨンの行政裁判所が除草剤「ランドアップ」の販売許可を取り消しました。それにともないフランス政府はランドアップを即、販売禁止にしました。フランスでは現在、グリホサートの販売自体は認められていますが、マクロン大統領は、2021年までにグリホサートの使用を全面禁止にする方針を掲げています。「私は、フランスがグリホサートを使わない世界初のワイン産地になると信じている」と述べています。
さらにドイツのメルケル首相も連邦議会で「グリホサートの使用は、いずれ終わるだろう」と述べていて、使用禁止に踏み切る可能性に言及しています。ドイツはグリホサートを開発したモンサントの親会社であるバイエルのお膝元ですが、禁止を求める声は多いようです。
ベトナム戦争で使用された枯葉剤で、甚大な健康被害を受けたベトナム政府も、グリホサートの使用を禁止すると同時に、輸入も禁止しました。
さらにアメリカでもカリフォルニア州がグリホサートを「発がん性物質リスト」に加えたのきっかけに、ニューヨーク州、フロリダ州、イリノイ州などで、自治体が所有する場所でのグリホサートの使用が禁止されるようになりました。
同時に製造会社のモンサントが訴えられる事例が相次ぎ、巨額の賠償金支払いを命じる判決が多数でる事態になっています。
日本はむしろ緩和?
さて、日本はどうなっているのでしょうか。
食品などのリスク評価をする内閣府食品安全委員会は、グリホサートに関して「発がん性や奇形性、遺伝毒性は認められなかった」とする評価書を2016年にまとめています。それにともない、2017年には一部の農産物の残留基準値を引き上げています。
たとえば、小麦は5.0ppmから30ppmへ、ライ麦は0.2ppmから30ppmへ、とうもろこしは1.0ppmから5ppmへと大幅に緩和されています。
人体への影響は?
心配なのは人体への影響です。海外では危ないと言われている農薬の規制緩和に不安を募らせる人は少なくありません。
農薬の発がん性のほかに、神経伝達物質として作用し自閉症を発症させる危険があると疑われていたり、ラットでは遅発性が確認されていて、妊娠中の母ラットにグリホサートを投与すると母子ではなんともなかったのに、孫ひ孫で障害が発生しています。
日本を含め世界で広く使用されている除草剤アトラジン(商品名ゲザプリム:シンジェンタ社(スイス))を、メスのワラビーに投与したところ、オスの赤ちゃんのペニスが通常より短くなったという研究が学術誌に掲載されました。体内のホルモンバランスを撹乱している証拠だとされています。
内分泌系はどの哺乳類でもよく似ているため、人にも当てはまる可能性が指摘されています。
これに対してシンジェンタ社は、投与されたアトラジン濃度はワラビーが環境中で接触する可能性のある濃度よりも高いと指摘し、「ありえないシナリオだ」と批判しています。
わたしたちにできること
では、身を守るために、わたしたちにできることは何でしょうか。
農薬の件に関していえば、国産だから安全ともいえないということです。むしろ海外では発がん性が指摘されていて、全面禁止にしようとする動きがあるのに、それに逆行しています。
それにはわたしたち消費者にも原因があるかもしれません。虫食い痕やキズのない野菜があたりまえで、そうでないと不良品というレッテルを貼ってしまいます。農産物は工業製品ではありません。自然を相手にしているため、常に同じものが一定に生産できるというわけにはいきません。農家も生活がかかっているため、売れなければやっていけないために、どうしてもそれに合わせて農薬を使ってしまいます。
無農薬でがんばっている農家を応援することも大切です。時間や手間を惜しまずに作っているので値段も高くなりますが、農業はすべての文明の基盤です。持続可能な農業のためにも大地がもっている生命力を維持できる無農薬、有機栽培は避けて通ることができないからです。
豊かに便利になった文明の恩恵を受けていることはありがたいことですが、行き過ぎた経済優先の効率だけを求めるやりかたには、NOを突きつける覚悟と勇気が必要なのかもしれません。